【起業の仕方】個人事業主と法人の初期費用・税金・資金調達を徹底比較!
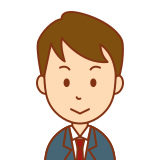
「起業の内容は大体決まったけど、具体的には何をしたら良いの?」
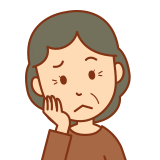
「起業をするときは会社を設立するの?お父さんは個人事業主らしいけど…」
いざ起業をする!と思い立った時に必ずといって良いほど悩む問題の一つとして
「個人事業主として事業をやっていくのか?それとも会社を設立して法人化していくのか?」
というものがあります。
・個人事業主(俗語としてフリーランスや個人での開業という言い方がある)
・法人(株式会社や合同会社のような、いわゆる皆が思う会社組織のこと)
のどちらで起業するかによって初期費用や税金の種類、資金調達のやり方などが大きく変わってきますので、まずは起業をする前に目的や目標、業種などを具体的にしてからこの記事を読み進めた方が読みやすいかと思います。
※起業をする前に目的や目標、業種についてを決めたい方はこちらをご参考にどうぞ
【簡単】誰でも出来る起業の仕方と手順を詳しく解説【必要なのは覚悟だけ】
では起業の手順をおさらいが終わったら、個人事業主と法人の経営の違いについてを初期費用や税金の種類、資金調達のやり方に絞って解説して行こうと思います。
B. 【業態決め】法人としてやるか、個人としてやるかを選択

よく「起業したら会社を設立しなくちゃいけないの?」と勘違いしてしまう事もありますが、別に会社にしなくても構いません。しかしながらこれにも大きく分けて2つ方法があるので、これは事前に決めてしまいましょう!
個人事業主 と 法人 二つのやり方がある
個人事業主(個人で開業、フリーランスとも呼ばれる)として起業するのか、法人(会社を設立する、株式会社や合同会社、NPO法人等がある)にして起業するのかの2択で悩むポイントはどこになるのか?それは、大きく分けて①初期費用と手続き、②会計処理と税金対策、③資金調達の面で違いが出てきますので、簡単に解説します。それぞれのメリットやデメリットを理解した上で起業の業態を決めていきましょう。
①初期費用と手続き
個人事業主の初期費用 手続き
初期費用ですが、個人ではほぼかからないと言って良いでしょう。手続きについても税務署に開業届を提出するだけで大丈夫です。
※個人事業主として起業する人は「個人事業の開業届出・廃業届出書」を管轄の税務署に提出しましょう。
法人の初期費用 手続き
法人化する時の初期費用は、株式会社を設立するのか合同会社を設立するのかで変わってきます。
これについては下記をご覧ください。
| 会社の設立に必要なお金 | ||
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 法人用印鑑代 | 3000円〜2万円 | 3000円〜2万円 |
| 収入印紙代金 | 0円(紙の定款は4万円) | 0円(紙の定款は4万円) |
| 公証人手数料 | 5万円 | 0円(不要) |
| 定款の謄本手数料 | 2000円程(250円/1page) | 0円(不要) |
| 登録免許税 | 最低15万円(資本金の0.7%) | 最低6万円(資本金の0.7%) |
| 手続き代行手数料 | 1万円〜2万円 | 1万円〜2万円 |
| 合計金額 | 約23万円程 | 約9万円程 |
費用はやはり、株式会社を設立する方がお高めになります。もちろんその分メリットはあるのですが、それは資金調達のところでご紹介します。
会社を設立した際の手続き
それとで続きですが、これがまた面倒なことにたくさんあります。
まずは会社設立格安センターという設立代行サービスに申し込んで会社関連書類を全部用意しましょう。
その際、自分の事業についてを提出する時に迷いそうなポイントについて解説しておきます。
| 会社名 | ぶっちゃけなんでも大丈夫です。でも領収書に書きやすい方が良いかも。 |
| 主な事業内容 | Googleで検索して、それっぽい文章を書いても良いですし、なんとなく書いて格安センターの人にメールで聞けばそれらしいものを書いてくれます。 |
| 会社住所 | 持ち家ならば最初は自宅でも大丈夫です。しかしアパートやマンションに住んでいる場合は、大家さんに確認をとるようにしましょう。もしもダメな場合はコワーキングスペースなどの住所を借りられる場所と契約するのが、固定費を抑えるコツです。 |
| 資本金の額 | 合同会社として小さく始めるつもりならば1万円で大丈夫です。株式会社であっても1万円から大丈夫ですが、100万円とかを入れてそれらしく見えるようにするのもありでしょう。ですが最初に入れる額はまだ経営に関係してこないので、そこまで意識しなくて良いでしょう。 |
そして格安センターから書類と印鑑が送られてきたら、次は
法務局、税務署、県税事務所、市役所(町役場)、銀行、労働保険事務所 等にいく必要があります。
これに関してはまた詳しい説明をご用意いたします。
②会計処理と税金対策
個人事業主の確定申告
会計処理については普通に確定申告をするのと変わりません。
※確定申告の詳しい解説についてはこちらをどうぞ
個人の節税対策
個人の節税対策については色々ありますが、まずは青色申告を選ぶことをお勧めします。
- 税金の申告の種類は2種類あります。それが青色申告か白色申告です。青色申告は多少自分で細かく経費を記録しておく必要がある代わりに、10万円または65万円の特別控除を受けられます。
- また、他にも住んでいる場所を事業に用いているのであれば水道光熱費に関しても一部は経費にする事が出来ますし、退職金制度のような小規模共済に入れば更に税金の控除を受けられます。
※個人事業主の税金に関することはこちらの記事を参考にどうぞ
法人の決算 税務申告
法人に関する会計処理はハッキリ言って専門家にお任せしましょう。
会社を設立した場合は、【決算書『財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)等を含めた会社のお金の使われ方や財務状況を示した書類の事』】を会計士さんに事業年度毎に作成してもらい、それに税理士の判子を貰うことで法人に関する税金の申告は済んでいる状態になります。この決算書を毎年作って納税していく事が会社の信用に繋がり、銀行からの融資の際にも重要視される書類になっていきますので、会計士さんと契約して会計処理をお願いするべきでしょう。因みに言うと、会計処理は会計士さんにお任せしても、基本的には会社の領収書をまとめて置いたり給料の支払いをしたりする経理作業は会社内部で行う必要がありますので、覚えておきましょう。
法人の税金対策
会社の法人でも青色申告と白色申告が存在します。ここでも青色申告を選んでおく事で受けられるメリットが存在します。そのうちの一つとして大きなものが、「欠損金の繰越控除」と呼ばれる制度で、今期分の赤字を来年以降に繰り越しておく事が出来る制度が使えます(最大10年繰越可能)。これを用いる事で、多く利益が出てしまいそうな事業年度に税金を減らす事が出来ます。
※その他の節税対策についてはこちらをどうぞ
会社設立(起業)したら法人青色申告を! 受けられるメリットや期限、手続きなどを徹底解説
さて、ここまで読んできた方は薄々気がつき始めていると思います。
「会社設立ってお金めちゃくちゃかかるし、正直言ってほぼメリットなんてないんじゃないですか?」
とこんなことを言う人も出てくるでしょう。確かに個人単位で小規模にビジネスをやり続けるとなると、個人事業主でやっていく方が経費も抑えられるし良い面もありますね。しかし次の「資金調達」の点を考えると、もしかしたら会社という業態も悪くないのでは?と思えるはずです。
③資金調達
資金調達とは、事業のための運転資金や設備資金、投資資金のためのお金を第三者から借りたり、投資してもらう事を指します。これに関しては、個人事業主は法人には全くと言って良いほど対抗出来ません。なぜでしょう?その理由を解説していくところから始めましょう。
個人事業主の資金調達
個人事業主としての資金調達で最も有りがちなのは、【銀行からの事業用ローン】だと思います。
しかし、まだ実績があまりない状態で銀行に行って、お金を借りることは出来たとしても正直多くのお金は借りられないのが個人事業主の現実です。なぜなら、個人事業主は社会的信用がそこまで大きくないからです。ここで言う社会的信用と言うのは、その人の人柄が悪いとかそう言う話ではなく、ズバリ【お金の余裕が無いし、収入源も安定していない】とみなされてしまうからです。
ここでわかりやすい例えを出すと、まだ仕事を始めて間もないサラリーマンが200万円の自動車ローンを借りる事が出来る理由は【その人が属している会社に対する信用があるから】に他なりません。会社は毎月毎月その人の銀行口座に給料をちゃんちゃんと払い続けてくれているとわかっているので、銀行も安心してお金を貸し出す事が出来るわけですよね。
それに対して個人事業主というのは、会社ほどの大きな後ろ盾はない事がすぐにわかってしまいます。元々個人事業主として長く生計を立てていたり、相当の年収がある事がわかっていれば別ですが、まだそんなに事業が安定していない時にお金を借りに来た人に対して銀行は「この人が少しでも稼がなくなったら返済が滞るかもしれない。」と思って、多くの資金を融資することはありません。
こういった理由もあって、個人事業主はお金を融資して貰うハードルは高めです。
法人の資金調達方法
法人の資金調達の方法ですが、ハッキリ言って個人とは比べ物にならないと言えます。ここでは銀行からの融資、投資家やVCからの資金援助や資金調達、クラウドファンディングという順番で見ていきます。
銀行からの融資 【上限3000万円まで!?】【合同会社も株式会社も】
まず、銀行からの融資の枠が大きいという点で法人は大きく有利と言えます。個人と違って社会的に信用が大きいと言える法人には多くの金融機関が「創業者資金の融資」「若い世代のための融資」「女性起業家に対する融資」等を準備してくれています。その運転資金や設備資金の上限額は多くが【運転資金のためのお金として1500万円まで、設備資金のためのお金として1500万円まで、計3000万円までの融資】というような融資を、無担保で借りられる場合もあります。(無担保というのは、お金を返せなくなった時でも何も銀行さんに取られませんよ〜という事。通常では持ち家の土地を担保に入れたりする場合もあるが、リスクは大きい。)
ここでひとつ私の知っている方が会社を作った例として、創業時の資金として700万円くらいを借りてから1年経たないうちに借り換えで、1600万円ほどの設備資金を借りていました。その機械の購入をする事でほぼ確実に〇〇円の稼ぎが毎月入ってくるというようなビジネスモデルの場合は、銀行もどんどんお金を貸し出します。
では次に、投資家やVCからの資金援助や資金調達を見ていきましょう。
投資家やVCからの資金援助や資金調達【主には株式会社】
まず投資家やVCとは誰の事かというと、
投資家とは【個人的に資金を潤沢に持っているので、その余裕資金を他の会社に投資してリターンを得る人】
VC(ベンチャーキャピタル)とは【資金が余っている投資家からお金を集めてファンドを作り、そのお金を成長生の高いベンチャー企業を中心に投資して利益を出し、投資家に還元する機関投資家】
の事です。
こういった会社が投資をするのは殆どの場合は【株式会社】に対しての投資になります。なぜかというと、それにはお互いが稼ぐ事が出来る仕組みが存在するからです。その仕組みとは
このように、新しく事業を始めたばかりの会社と投資家やVCとの関係は持ちつ持たれつの関係なのです。
これはつまり、投資家やVCに将来性があると判断された場合は、最終的にとてつもない資金を調達して大きく事業を成長させていく事が可能になります。これが初期費用が多くかかっても株式会社を設立して事業を展開していく大きなメリットと言えます。
しかし、投資家やVCの人とは中々お目にかかれるものでもないのと、投資を引き出すためには相当な覚悟と情熱がある事を認めて頂く必要があるので、ハードルは高いと見て良いでしょう。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとはここ数年で急激に伸びてきた資金調達方法です。インターネット経由でこれから開発したい商品を宣伝して資金を不特定多数から集めて、その見返りとして支援者の方々にはその商品を無料で提供したりする。という今の時代にマッチしている資金調達方法と言えそうですね。これは個人でも可能ですが、元々の知名度が無かったり、本気度が伝わるかどうかという点においても、やはり法人化してある方が資金を集めるのに適していると思いましたので法人の欄に載せておきます。
クラウドファンディングでは事業の種類も調達金額の大きさも本当に様々なものが存在します。日本で有名になってきているクラウドファンディングプラットフォームとしてCAMPFIRE(キャンプファイア)というサービスがありますので、気になる方は一度見てみることをお勧めします。
しかし注意点としては、クラウドファンディングの成功のコツをちゃんと勉強してから望まないと、思ったように資金が集まらずに頓挫してしまう事が多々あるので、まずはこのオリエンタルラジオ中田さんの動画で勉強しましょう。
ここまでで、個人事業主と法人の違いは大まかに理解出来たかと思いますので、まとめていきたいと思います。
個人事業主と法人の違い まとめ

個人での場合と法人での場合で、様々なメリットとデメリットが存在している事が理解できたと思います。
おさらいも込めて、もう一度まとめておきましょう。
個人事業主の場合
メリット 初期投資が格段に安い
デメリット 収入が上がるほど税制の優遇が弱い / 資金調達方法が限られる
つまりお金はかからないが、お金は借りづらい。
法人の場合
メリット 売上が上がれば上がるほど税制面でのメリットが大きくなる /
社会的信用が強く資金調達方法が豊富(銀行からの融資や投資家、VC、クラウドファンディングなど)
デメリット 初期投資(10〜25万円程)/ 会計処理(年間20万円程)にお金がかかる
つまりお金はかかるが、お金は比較的借りやすい。
どちらにも良い面があるので、あなたの起業にあった手段を選んでいく事が大事ですね。
おすすめの方法
因みに私が思うおすすめの方法は【合同会社を設立しておく事】ですね。理由は、初期費用が株式会社よりも安くて、個人事業主よりは社会的信用があるので銀行からの融資も受けやすいと言えます。
そして事業が安定してきてから、更に事業を大きくしたいので投資家やVCから出資を受けたいと思った際には、個人事業主から法人になるよりも手続きが多くないので、合同会社は意外と良いとこどりをしている形態だと思います。
どうぞご参考にしてみてください。
では。
※ここまでで
ステップA【コンセプト決め】起業の下準備として最低限決める事【目的、目標、業種選び】
ステップB【会社として始めるのか、個人として始めるのか】を終えたので、
ステップC【営業開始】最初の一歩として、具体的にやるべき事
という疑問を解決していきましょう。
※起業とは何か?をより詳しく知りたい方はこちらをご参考にどうぞ
【起業とは】という疑問を解消!メリットとデメリットをわかりやすく解説






コメント
[…] […]
[…] […]
[…] […]